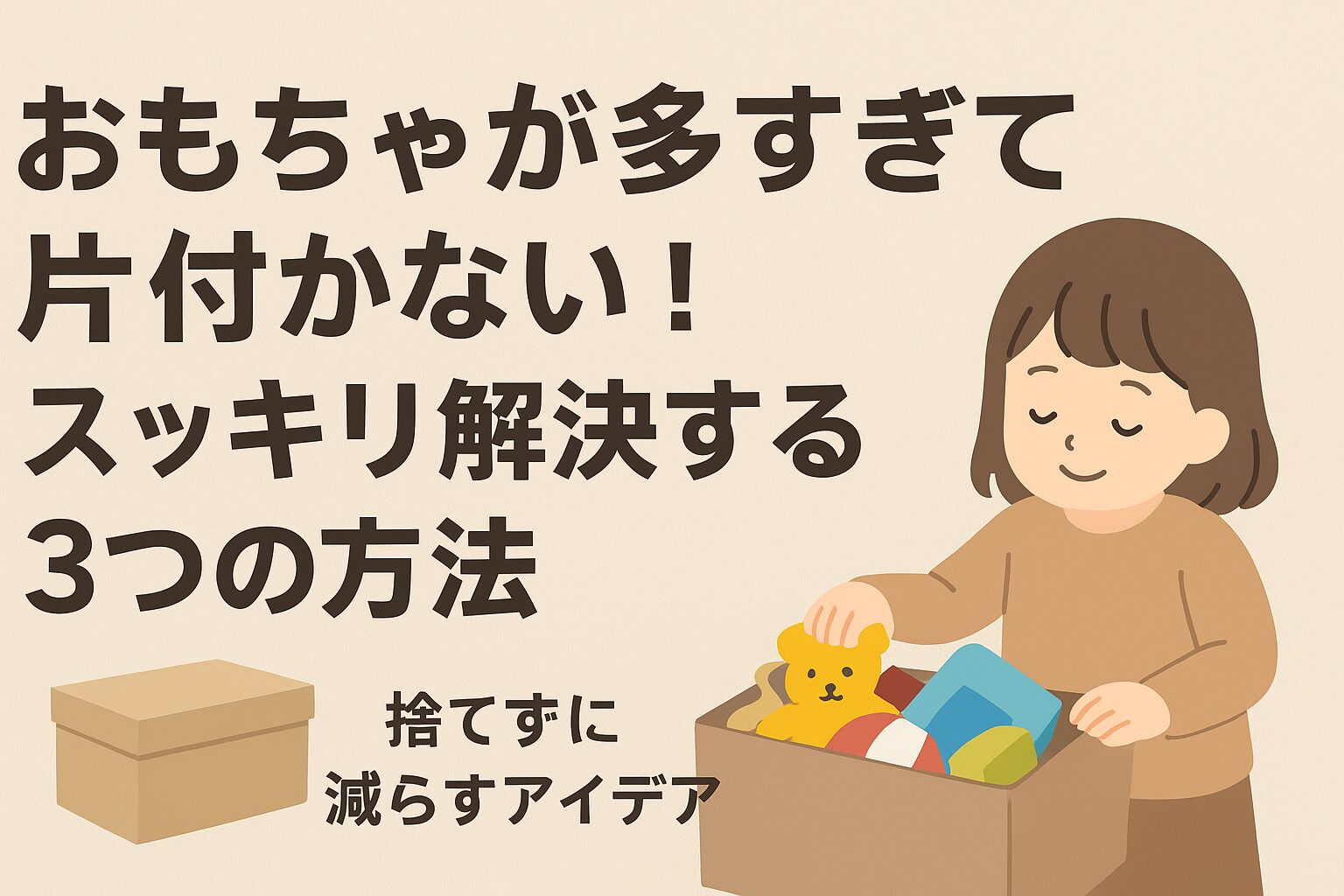子どものおもちゃ、気づけば部屋いっぱいになっていませんか?
「片付けてもすぐ散らかる」「捨てるのはかわいそう」──そんな悩み、私も同じでした。
でも、ある考え方と仕組みを取り入れたことで、
“捨てずに減らす”おもちゃ整理ができるようになったんです。
この記事では、実際に我が家で効果のあった
「おもちゃが多すぎ問題をスッキリ解決する3つの方法」を紹介します。
Contents
1. おもちゃを「現役」「おやすみ」「卒業」に分ける
最初にやるべきは、“全部を片付ける”ではなく“分ける”こと。
子どもが遊ぶおもちゃを3つに分類してみましょう。
-
現役:毎日遊ぶ、今好きなもの
-
おやすみ:たまに遊ぶ、気分次第のもの
-
卒業:もうあまり使わない、興味が薄れたもの
「おやすみ」のおもちゃは箱や袋に入れて一時保管。
3か月経っても遊ばなければ、“卒業”のサインです。
そしてこの**「卒業おもちゃ」**の扱い方が大切です。
すぐ捨てるのではなく、「誰かにバトンタッチ」する感覚で循環させましょう。
🎁 卒業おもちゃの行き先アイデア
-
フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)で出品
-
保育園のバザー・児童館・支援センターに寄付
-
友達や親戚の小さい子に譲る
-
サブスクを利用して「レンタルで遊ぶ → 返す」に切り替える
こうすることで、モノが減るだけでなく、
「大切に使ってくれる人に渡せた」という満足感も得られます。
我が家ではこの仕組みを取り入れてから、
おもちゃの量がぐんと減り、子どもも遊ぶ時間が長くなりました。
2. 収納は“見える”より“分ける”を意識
おもちゃが片付かない最大の理由は、「収納量」ではなく「分類不足」。
いくら大きな収納箱があっても、
いろんなジャンルが混ざっていると、子どもは探せません。
そこでおすすめなのが、カテゴリ別収納+ラベルです。
🧺 例:
-
ブロック
-
おままごと
-
車・電車
-
ごっこ遊び

こんな感じで、ボックスにラベルを貼るだけでOK。
透明ケースや浅型トレイだと、中身が見えてさらに使いやすいです。
💡 無印良品やニトリ、IKEAなどの収納ケースもおすすめ。
子どもが“自分で戻せる仕組み”を作ると、
自然とお片付けの習慣も身につきます。
3. “増やさない仕組み”を作る(←これが一番大事!)
おもちゃが増えるのは、買うスピードが「卒業」より早いから。
つまり、買う量を減らすのではなく、
「循環」させる仕組みを作るのがポイントです。
その解決策として、我が家では**おもちゃのサブスク(定額レンタル)**を活用しています。
🎁 おもちゃのサブスクとは?
月額料金で知育おもちゃをレンタルできるサービス。
遊び終わったら返却し、次の新しいおもちゃが届く仕組みです。
買いすぎることもなく、常に子どもの発達に合ったおもちゃで遊べるのが魅力。
特に「トイサブ!」を使い始めてからは、
収納棚がスッキリして、子どもも飽きずに遊ぶようになりました。
🔗 関連記事
▼ おもちゃレンタルを比較してみたい方はこちら
▼ 実際に使ってみたレビューはこちら
まとめ
おもちゃが多すぎると、部屋も心も疲れてしまいます。
でも、
1️⃣ 分けて
2️⃣ 片付けて
3️⃣ 増やさない仕組みを作る
この3ステップで、驚くほどスッキリします。
「捨てる」ではなく「循環させる」育児スタイルで、
家も子どもも笑顔にしていきましょう😊
まとめのポイント
| 悩み | 解決策 |
|---|---|
| おもちゃが多すぎる | 分類+一時保管 |
| 散らかる | カテゴリ収納+ラベル |
| 増えすぎる | サブスクで循環 |